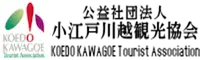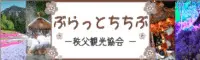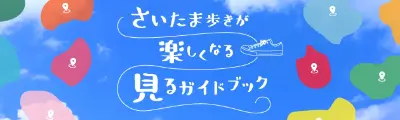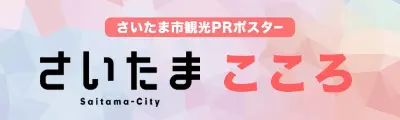さいたま見沼の竜伝説を探る!
所要時間
2時間
主な交通手段
バス・徒歩
見沼エリア
緑豊かな見沼田んぼ。この地域に古くから伝わる竜伝説にまつわるスポットを巡ります。
最初の目的地は、見沼の歴史を感じる氷川女體神社。参拝後は、古くから神社で行われていた神事を今に伝える「磐船祭祭祀遺跡」と併設された見沼氷川公園を散策します。見沼代用水西縁沿いの桜回廊を歩き、さいたま新都心まで見通すことができる見沼大橋を渡って芝川を超え、見沼代用水東縁にある国生寺や総持院まで歩きます。
見沼の自然と歴史を肌で感じることのできるコースです。
-
START
浦和駅
10:0035分 -
1
氷川女體神社
10:4020分+「埼玉の正倉院」とも呼ばれる氷川女體神社!
-
230分+
-
3
国昌寺
11:30
戦国期に心巌宗智によって開かれ、二代目住職の能書家として知られた大雲文龍によって再興された曹洞宗の寺です。山門は開かずの門として有名で、欄間の龍の彫物は、見沼の竜神伝説を伝えています。 <山号> 大崎山 国昌寺 <宗派> 曹洞宗
このスポットの詳細情報はコチラ!15分+ -
GOAL
総持院
11:45
天正5年(1577)に法印良秀によって開かれた真言宗の寺で、大きな山門(鐘楼門)が特徴です。別名ボタン寺として知られ、境内には約400株のボタンが植えられ、シーズン中は見事な花園になります。 <山号> 阿日山宝袋寺 総持院 <宗派> 真言宗智山派 <本尊> 地蔵菩薩
このスポットの詳細情報はコチラ!